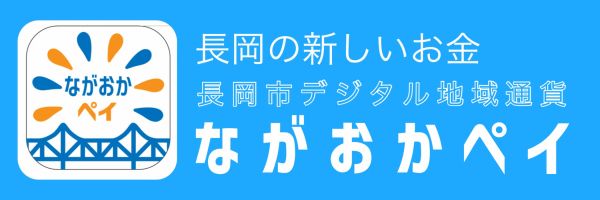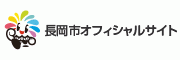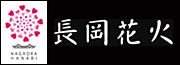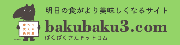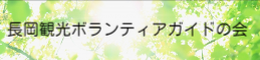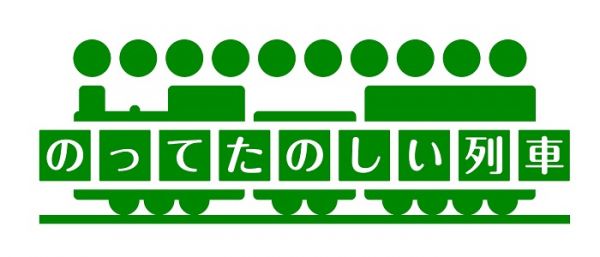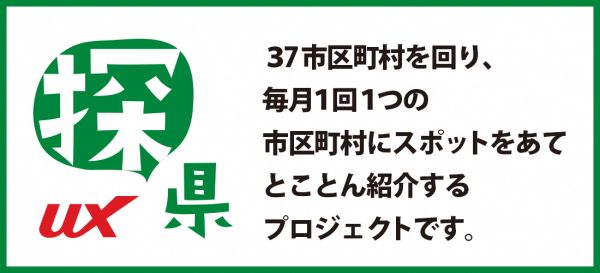-
位 1
高龍神社
商売繁盛の神様として、県内からそして全国各地から参拝者が絶えない神社です。太田川の上流で三方を山に囲...
-
位 2
平潟神社
長岡市の中心部にある平潟神社は今でも市民の守護神として多くの人たちに敬まわれている。境内には長岡空襲...
-
位 3
金峯神社
長岡市の北西、長岡大橋と蔵王橋の中間の信濃川右岸べりにけやきの大木が茂る一帯があり、その森の中にかつ...
-
位 4
少彦名神社
かつて沼地だった神田には薬師様がまつられていたが、神仏分離により少彦名神社がおこったといわれる。 ...
-
位 5
宝徳山稲荷大社
天照白菊宝徳大神をまつるこの神社は、文政年間(1820頃)中之岳銀が峰から、この地奥之院長者原に遷営...
-
位 6
悠久山公園
市民から「お山」の愛称で親しまれている悠久山公園は、この地をこよなく愛した長岡藩3代藩主牧野忠辰(た...
-
位 7
栄凉寺
長岡藩軍事総督として北越戊辰戦争の指揮をとった河井継之助をはじめ、12代藩主牧野忠訓や北越戊辰戦争後...
-
位 8
南部神社
南部神社の祭神は天香具土命(あまのかぐつちのみこと)で養蚕の神。別名「猫又権現」と呼ばれ、かつては蚕...
-
位 9
蒼柴神社
かつて越後の国を治めた長岡藩の要となった長岡城。その本丸の一画に鎮座していた神社こそ、この蒼柴神社で...
-
位 10
金峯神社の王神祭
毎年11月5日信濃川でとれた鮭を神宮が直接手をふれないように鉄箸と包刀とで調理し、鳥居の形にして神前に供える全国で...
-
位 11
西福寺
慶応4年(1868)5月19日、榎峠の攻略が難しいと判断した新政府軍は、大島、槇下から信濃川を渡河し...
-
位 12
前島神社
小千谷談判の翌日、前島村の警備にあたっていた友人の川島億二郎(のちの三島億二郎)に談判決裂の結果を伝...
-
位 13
諏訪神社
栃尾がおこった頃からの鎮守。御祭神は建御名方命(たけみなかたのかみ)で地上の支配者である大国主神(お...
-
位 14
医王山 遍照院 寛益寺【2022年5月8日(日曜日)、12年に一度の御開帳】
寛益寺(かんにゃくじ)は、養老2年(718年)に行基によって開基されました。 近世以前から人々の信...
-
位 15
如意山 照明寺
永承2(1047)年、高野山龍光院の僧侶がこの地に庵を結んで観音像を安置したのが始まりです。 毎年...
-
位 16
南泉院
真言宗智山派に所属する當山の、山号は海雲山、寺号を興善寺、院号を南泉院と称します。 須弥壇正面の本...
-
位 17
昌福寺
戊辰戦争時下、寺院も軍施設として供用される中で、昌福寺は負傷者を手当てする軍病院として利用されました...
-
位 18
二面神社
白山媛神社の境内にあり、明徳2年(1391)5月、土地の漁師平三郎が夢枕に立った神のお告げにより、海...
-
位 19
寺泊 養泉寺
文禄3年(1593)年信濃国より寺泊に移住した真宗大谷派の寺です。階段を登った境内には樹齢100年を...
-
位 20
普済寺
三間豊蔵、牧野金太郎ら、北越戊辰戦争に参戦し、年若くして散った少年隊士の在名碑があります。 石段を...
-
位 21
永閑寺
河井継之助は長岡城奪還を目指し、新政府軍が占領していた今町に攻め入り、激戦が繰り広げられました。 ...
-
位 22
八幡宮
村の鎮守様として「はちまんさま」と呼ばれ古くから親しまれている。 拝殿前にある、震災時でも倒れるこ...
-
位 23
普門山 千蔵院
地名の由来になった千手観音が祀られている。 現住所は柏町だが、戦前は中千手町。長岡藩の祈願寺として...
-
位 24
大悲山 根立寺
天和年中(1681〜83)の頃に流行した眼病から民を救った観世音(かんぜおん)。 正観音は住職一代...
-
位 25
日光社
長岡城奪還作戦の第一功労者、鬼頭熊次郎の碑がある。32石取りのこの藩士は、貧しさのため八丁沖で魚を採...